小太刀との出会い
四段から必須になる「小太刀」。
初めて習ったときの第一印象は――「何かカッコいい!」。
しかし実際に構えてみると、腰に手を当てっぱなしになってしまったり、解く時に左手を下ろすのを忘れてしまったり。基本の所作からつまずく私。
🗣️恩師の金言
「小太刀は、上・下・中と覚えるといいよ」
なるほど、と思いつつも、これが奥深い世界の始まりでした。
⸻
打太刀で味わった驚き
最初に教えていただいた先生は、最近の試合で刃引きの演武を披露されたほどの達人。
打太刀をお願いすると――
「あれっ、私何もしてない…?」
まるでダンスでリードされているかのように自然に動けてしまう。
小太刀の一本目も、二本目も、スルスルと動けて「簡単かも?」と錯覚するほど。
しかし他の方と合わせた瞬間に現実が…
「あれっ?できない!」
そう、先生が凄すぎただけだったのです。
⸻
仕太刀の難しさ
一本目は面を返して残心。そんなに難しい動きではない。
二本目は下段から攻める。
「手のひらの小指球で鼻先を擦り上げるように」と教わり、軽く持つと高い良い音が鳴る。
⭕️「カーン!」
❌「ガチッ!」
けれど本番では「カーン!」でも「ガチッ」なく「スカッ」…苦笑。
⚠️残心は腕を上から抑える。右足から下がる!
木刀の質や持ちやすさでも音や感覚が変わります。おすすめはこちら↓
三本目のすり上げ・すり落としは特に苦労しました。
打太刀が来るのを待っていたら、擦り上げにならないし。
しかも初対面の相手と呼吸を合わせるのは本当に難しい。
胴にくるのを、すり流し、すり込み。
刃の方向と、どこですり流し、すり込みをするのか?
左足!
身体の向きを、最初のすり流しの時に回転させるようにするとやりやすい。
残心は腕を下から抑えて、関節を決めるように。
⚠️左から下がる!!
形はただの動作ではなく、気と技を合わせる稽古だと痛感しました。
⸻
稽古を通じて学んだこと
• 擦り落としは「軽すぎず、強すぎず」
• 刃の方向と足さばきが肝心
• 残心でどちらの足から下がるか、細部まで確認
大人になってから稽古すると、意味や視線、木刀の使い方を意識できる。
それでも形は奥深く、「溜め」や「緩急」を理解するにはまだまだ修練が必要だと感じました。
⸻
リバ剣お父さん「色んな人とやってみた方がいいっすよ!」
これが本当に審査で役に立った。
特に若者はスピードが速いように感じた。審査で当たるのは同世代だから大丈夫だろうと思う・・・
審査前に稽古してくださる方がずっと同じだとびっくりすることもあると思う。
剣道形だけはしっかりやっておかないと、審査はもちろん合格しないし、相手にも迷惑をかけることになる。
笑いありの夫婦バトル
何度も一緒に稽古してくれたのは、道場の先生と、私をリバ剣に誘ってくれたご夫婦。
その夫婦が形を合わせると――意見が真っ二つ!
家で何回稽古しても合わないから旦那がおかしい!と怒りの奥さんからの苦情を前もって聞いていた。
道場にてーーー
奥さん「こうでしょ!!」
旦那さん「いや、そっちが違う!」
奥さん「はあぁ〜〜!!?〜ちゃん(私)、どう思う!?」
旦那さん「いやいや、こうですよね!?」
板挟みの私www
「奥さんの方だと思う…先生、どっちが正しいんですか?」
先生「奥さんだね」
奥さん「ほらぁああ〜〜〜!」(ドヤ顔)
旦那さん「えええ〜!?」
大爆笑。
「剣道形で離婚の危機よ!もう!!!」
先生にしっかり指導してもらう旦那さんww
一緒に昇段しようね!
⸻
まとめ:形は人と人をつなぐ
審査を受けて実感しました。
剣道形は、一人でできるものではなく「相手と呼吸を合わせること」がすべて。
だからこそ、色んな人と合わせて稽古することが大切なのだと。
これまで一緒に稽古してくれた先生方、そして仲間たちに感謝。
一歩ずつ、四段に向けて歩んでいきます。
これから小太刀を稽古する方へ。おすすめの木刀はこちらです↓
ブログランキングに参加しています!


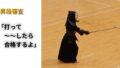
コメント